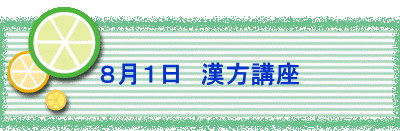
中国の伝統医学、いわゆる漢方は、医学だけではなく固有の世界観に基づいていて、また飲食・生活習慣・感情などの日常生活に密接な関係を持っています。ある病気に特定な薬を飲んだほうがよいという指導があっても、中国人の考え方を説明される機会はなかなかありません。
語林教室の樋口は、中国語がわかり、国際中医薬師の免許を所有しています。8月1日(日)、本教室の6名の方に漢方の世界観・漢方医による病因に対する理解・風邪の種類・足裏のツボなどをテーマに充実した2時間の講演をしました。
まず、日本の曜日の由来でもある木・火・土・金・水の五行思想から始まりました。相生・相克という五行の相互関係の説明の後、金-肺・木-腎という五行思想と五臓の対応関係を説明し、人間の喜怒哀楽が五臓六腑にそれぞれ影響することを詳しく説明しました。過度な喜びが心(臓)を傷つける(「喜傷心」)ということに、皆さんはびっくりしました。
たとえば、風邪は中国語で「感冒」と言います。漢方によると、「感冒」は必ずしもウイルスの進入という単純な原因によるものではありません。人体の内部の状況(「虚証」)と環境(「実証」)の相互作用によって生じたものと考えます。環境的な原因といえば、「風邪」「寒邪」「暑邪」などが挙げられました。異なる症状によって医者が病因を判断し、「対症下薬」をするのです。漢方の奥深さが興味深かったです。
また、足の裏は人体の縮図のようなものであり、親指からはじまってそれぞれの指は、頭・鼻・目に、下にいくと、胃腸・膀胱・生殖などに対応しているので、パソコンで目が疲れたとき、真ん中の足指を押すと疲れが取れるという話も実用的でした。
自由質問の時間に、中国で漢方薬の入手方法などが聞かれました。また中国で中医がどのように普及し、根付いているかという話にもなりました。語林教室の他の講師が授業中に皆さんに勧めた「目の体操」の話題に上がり、意外にも、生徒さんがそれを実践しているとのことでした。
自分の体の器官の働き・体と感情・体と環境の関係をよりよく理解することは、現代人が求める大きなテーマの一つです。漢方の認識を正確に・分かりやすく伝えるには、中国語・中国での生活経験が不可欠だと思われます。
今後も月1回のイベントで漢方講座も開きます。どうぞご期待ください。
 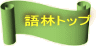
|