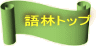7月4日(日)「中国語で調理実習」というイベントを開催しました。
先生は前回同様、「東北餃子楼」のコックさん(賀さん)とスタッフ2名(彭さん姉妹)。作り方が簡単な「涼菜(liang2cai4)/中華風オードブル」だったせいか、コックさんの説明もシンプルでした。参加者はほとんど上級クラスの方でコックさんの言うことはほとんどわかりましたが、たまによくわからない言葉があると聞き返し、言い方を換えてもらったりしながら粘り強く理解に努めました。
3脚並べて広くしたテーブルに、大きなまな板、調味料(塩・白砂糖・味の素)の入った小皿、黒酢の瓶が置かれます。
最初に作ったのは、「干豆腐[糸糸](干し豆腐の細切りの酢の物)」。下茹でした干豆腐(gan1dou4fu)とにんじんときゅうりの細切りをお箸で混ぜます。そこに調味料を加えてさらに混ぜ合わせて、お皿に盛り合わせ、白ごまを一振りしたら完成。あっという間にできあがりましたが、次々に質問が飛び出します。
-この干豆腐は茹でてから切るんですか?
-切ってあるのを買ってきます。
-辛いのが苦手なんですけど、ラー油は必ず入れなきゃだめですか?
-ごま油だけでもいいですよ。
その次は、参加者が同じものを同じように作ります。でも辛いものが苦手な方がいらっしゃったので、辛くない味付けにして作りました。応用もできてラッキーだったと思います。
それから「老醋花生菠菜(ピーナッツとほうれん草の黒酢和え)」も順調に作り終え、否、もしかしたら実習は黒酢がちょっと多かったかもしれませんが、たくさん酢を摂るのは身体にいいですよね・・・・・・。
そしてリクエストが多かった「蒜泥黄瓜(きゅうりの酢の物にんにく風味)」に取り掛かります。あの大きな中華包丁の平たい面をたたきつけるようにきゅうりをバンと叩いて砕き切る場面には熱い注目が集まりました。
-もし中華包丁がなかったら、瓶を代用してもいいですか?
-いえ、包丁で乱切りすればいいです。
意外にあっさりした答えが返ってきたので、少しがっかりしましたが、「それなら是非ここできゅうりを叩きたい」と参加者がコックさんを真似ました。きゅうりに和えるにんにくのみじん切りも、包丁で叩くように押しつぶしてから細かく刃を入れます。紅一点の参加者も華奢な手に重たい中華包丁を握って挑戦しました。
日本で割と一般的な「皮蛋(ピータン)豆腐」ですが、今回は「手抓(shou3zhua1)」、お豆腐を手でつかみようにしながら潰して混ぜ合わせるという作り方を教わりました。みじん切りしたピータン・ザーサイ・葱と調味料をお豆腐の上に載せます。そして手で豆腐を潰しながら調味料が全体に行き渡るようによくまぜます。参加してくださったHさんのように、小さいお子さん(6歳と4歳)がいらっしゃるお家では、粘土遊びのようにお料理ができる作り方です。
最後は「賀家涼菜(賀さん流白菜の酢の物)」。「家常涼菜」とコックさんはおっしゃいましたが、賀さんが教えてくださったので、「賀家」としました。千切りした白菜・干し豆腐・にんじん・きゅうりを材料にしますが、ここでの主役は白菜でした。芯の歯ざわりがポイントなので、白菜は内側の葉の少ない部分を使います。
-これは「小白菜」ですか?
-いいえ、「大白菜」です。
-あ、ふつうの白菜、「大白菜」の芯なんですね。
-「小白菜」と「大白菜」は別のものなんですよね。
-そうです、それぞれ種類が違う野菜です。
白菜の内側だけ取り出されたのを見て、中国にある「小白菜(xiao3bai2cai4)」かと勘違いしました。そこで参加者の半数がコックさんに向かって、これは日本の白菜、中国でいう「大白菜(da4bai2cai4)」の内側であるということを言葉を尽くして確認しました。
それからビールやウーロン茶をいただきながら、楽しい試食タイム。参加者が模倣して作ったのは、全てラー油や紅油(油に一味もしくはとうがらしを入れて辛味をつけたもの)を入れませんでしたが、十分においしくできました。