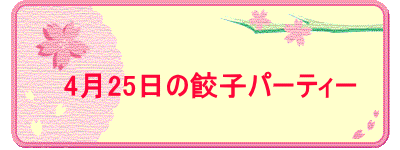
去る4/25(日)、語林教室は、新中野の「東北餃子楼」で餃子教習会を開きました。
先生は東北餃子楼の女性スタッフ3名とコックさん1名。参加者全員が中級以上だったため敢えて最初から最後まで一言も日本語での説明はありませんでしたが、先生たちが優しくはっきりと短い言葉で説明してくださったのでわかりやすかったです。和気藹々とした中で、参加したみなさんも日ごろの勉強で培った実力を発揮できました。
参加者15名は、毎日ごはんを作っている方から「はじめてのお料理」という方までと幅広かったですが、一様にエプロンを着け手を洗って、さあ開始! 80~90個分の餃子の皮を作るわけですから当然とはいえ、いきなり直径20センチもの大きなボールいっぱいに入った粉を見て、一瞬後ずさりした人もいました。先生は静かにぬるま湯を粉の中に注ぎ、お箸・次には手でこねていきます。一人ずつ順番にこねますが、思ったよりも水は少なめで、その生地の固いこと。それでも全身の力を入れるように、果敢にこねていきます。
濡れ布巾をかけて生地を寝かせている間、今度は男性のコックさんが具の作り方を教えてくださいます。今日作るのは「三鮮餃子」。具材は豚肉・卵・エビ・ニラで、東北地方の代表的なものだそうです。
まずひき肉に塩・味の素をふりかけ、それからごま油が大量に入ります。先生は生徒たちの驚きを全く気にせず、その次にオイスターソースもたっぷり入れ、お箸で混ぜました。ここでも一人ずつ混ぜていきますが、同じ方向に混ぜるよう指示されます。緊張したのか狙ったのか、最初の方がいきなり反対方向にお箸を回すというちょっとびっくりの楽しい一幕もありました。
それから炒り卵・ニラ・エビも入れ、同様に混ぜて具の完成。
そして餃子の皮作りが始まります。女性の先生と入れ替わり、寝かせていた生地を四つに分けてこねます。「陶芸の粘土をこねるのと同じですね。」とおっしゃった方がいましたが、たしかに菊練りにそっくりです。
それをひも状に延ばし、ひとつ分の量に指でちぎります。
80~90個分の餃子の皮を作るわけですから当然とはいえ、いきなり直径20センチもの大きなボールいっぱいに入った粉を見て、一瞬後ずさりした人もいました。先生は静かにぬるま湯を粉の中に注ぎ、お箸・次には手でこねていきます。一人ずつ順番にこねますが、思ったよりも水は少なめで、その生地の固いこと。それでも全身の力を入れるように、果敢にこねていきます。
濡れ布巾をかけて生地を寝かせている間、今度は男性のコックさんが具の作り方を教えてくださいます。今日作るのは「三鮮餃子」。具材は豚肉・卵・エビ・ニラで、東北地方の代表的なものだそうです。
まずひき肉に塩・味の素をふりかけ、それからごま油が大量に入ります。先生は生徒たちの驚きを全く気にせず、その次にオイスターソースもたっぷり入れ、お箸で混ぜました。ここでも一人ずつ混ぜていきますが、同じ方向に混ぜるよう指示されます。緊張したのか狙ったのか、最初の方がいきなり反対方向にお箸を回すというちょっとびっくりの楽しい一幕もありました。
それから炒り卵・ニラ・エビも入れ、同様に混ぜて具の完成。
そして餃子の皮作りが始まります。女性の先生と入れ替わり、寝かせていた生地を四つに分けてこねます。「陶芸の粘土をこねるのと同じですね。」とおっしゃった方がいましたが、たしかに菊練りにそっくりです。
それをひも状に延ばし、ひとつ分の量に指でちぎります。
 ちぎった生地を丸めて上から軽く押し、麺棒で延ばします。腕に覚えがある人(意外に男性も多かったです)が挑戦しました。その横で具を包み始めます。延ばすのも包むのも、みなさん上手でした。
注文した料理をいただきながら、茹で上がるのを待ちました。上手に包めた餃子は水餃子に、具が出てきてしまいそうなのは蒸し餃子に調理され、黒酢とおしょうゆをつけていただきました。
教習会は1時間ほどで終わり、同じ場所で懇親会をしました。次の教習会で作ってみたいという料理をメニューの中からいくつか選びました。
エプロンをはずさずにお店をうろうろしていたある参加者が他のお客さんにお店の人と勘違いされて話しかけられました。思わず「我不是服務員。」と中国語で返すと、「言葉がわからないのね。」と解釈されるなど、すっかり中国語に親しむことができた様子でした。
ちぎった生地を丸めて上から軽く押し、麺棒で延ばします。腕に覚えがある人(意外に男性も多かったです)が挑戦しました。その横で具を包み始めます。延ばすのも包むのも、みなさん上手でした。
注文した料理をいただきながら、茹で上がるのを待ちました。上手に包めた餃子は水餃子に、具が出てきてしまいそうなのは蒸し餃子に調理され、黒酢とおしょうゆをつけていただきました。
教習会は1時間ほどで終わり、同じ場所で懇親会をしました。次の教習会で作ってみたいという料理をメニューの中からいくつか選びました。
エプロンをはずさずにお店をうろうろしていたある参加者が他のお客さんにお店の人と勘違いされて話しかけられました。思わず「我不是服務員。」と中国語で返すと、「言葉がわからないのね。」と解釈されるなど、すっかり中国語に親しむことができた様子でした。
 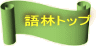
|